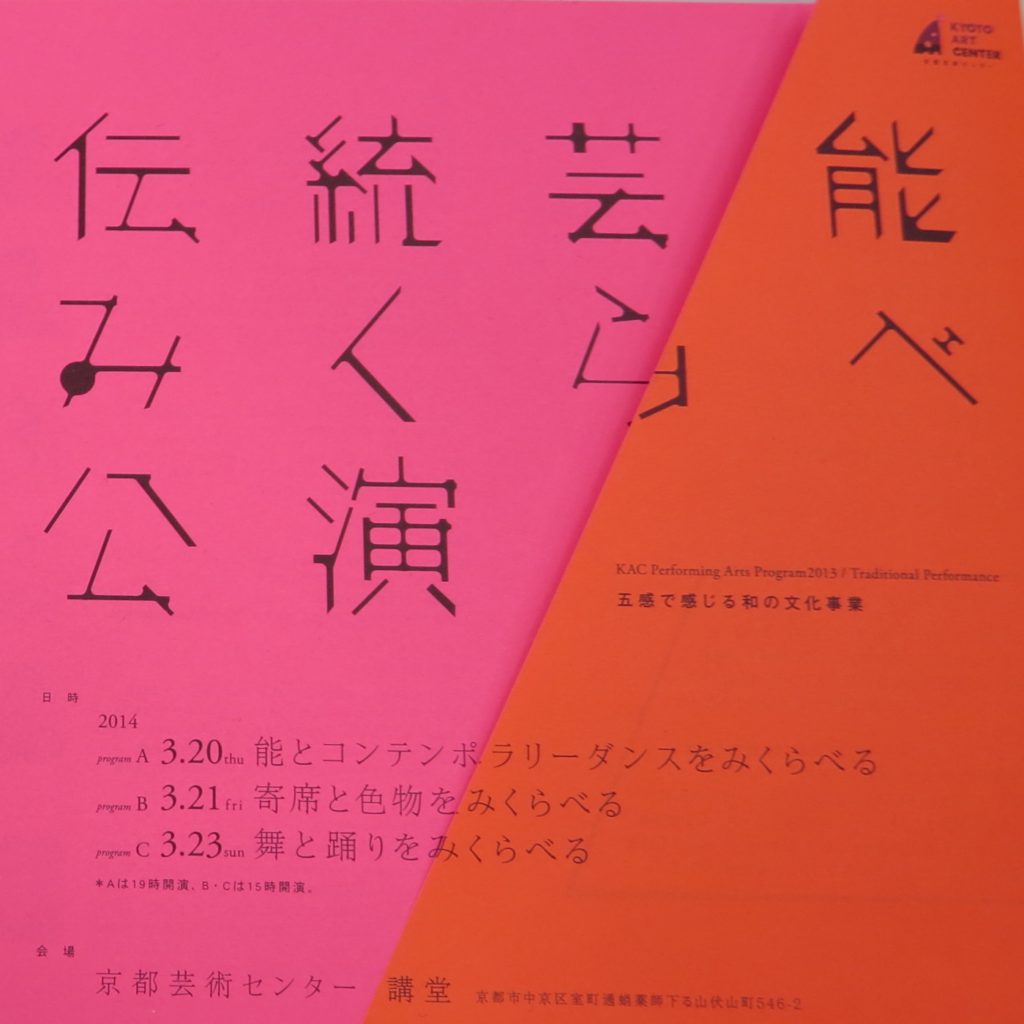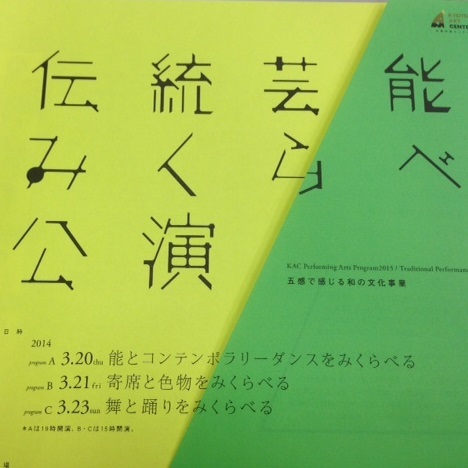SCROLL
五感で感じる和の文化事業 「伝統芸能みくらべ」公演
- ジャンル
- ダンス/伝統芸能
- カテゴリー
- トーク/レクチャー/公演
- 開催日時
- 2014年3月20日(木)~2014年3月23日(日)
- 会場
- 京都芸術センター 講堂
- 料金・その他
- 有料
- 事業区分
- 主催事業
現代に受け継がれてきた伝統芸能。
その姿は、時代を経て少しずつ更新しながら、今にいたっています。「伝統芸能みくらべ」公演では、他の分野と出会いみくらべることで、その芸の本質である精神性や構造に迫ります。
http://481engine.com/rsrv/webform.php?sh=2&d=f60565d196
*システム協力:シバイエンジン
Program.A
「能とコンテンポラリーダンスをみくらべる」
能は600年かけて研ぎ澄まされてきた最小限の動きのなかで、人間の本質や情念を語ります。舞踏を出自とする伊藤キムさんと、バレエを出自とする寺田さん、別の「踊る」身体をもつふたりが、能の仕舞に挑戦!!能とコンテンポラリーダンスをみくらべます。
日時:3月20日(木)19:00開演、18:30開場
出演:シテ:河村晴道、味方團、田茂井廣道、深野貴彦
笛:竹市学 小鼓:吉阪一郎 大鼓:河村大
ゲスト:伊藤キム(振付家、ダンサー)、寺田みさこ(振付家、ダンサー)
司会:志賀玲子(舞台芸術プロデューサー)
演目:舞囃子「松風」、仕舞「松風」
Program.B
「寄席と色物をみくらべる」
落語の寄席は、落語以外の演芸を朱で書き、それらを「色物(いろもの)」と呼びました。「女道楽」は女性芸人が唄や踊り、話術をもって披露する芸能のこと。大正期に色物として全盛を迎えました。その後、現在の漫才や漫談へとつながっています。いちど途絶えた「女道楽」を復活させて内海英華さん、日本で最初の女流噺家である露の都さんとともに、その時代の演芸をみくらべます。
日時:3月21日(金・祝)15:00開演、14:30開場
出演:露の都(落語家)、内海英華(寄席囃子三味線/女道楽師)
司会:小林昌廣(情報科学芸術大学院大学教授)
Program.C
「舞と踊りをみくらべる」
「舞踊」は、明治になってできた新造語で、舞と踊りを合体させた言葉。
「舞」は神楽や舞楽にはじまり、能で一つの完成形をみます。その舞の変形としてできたのが「踊り」。「舞」は様式をもって身体を集中させ緊張を高めていくのに対して、「踊り」は様式から身体を解放させていきます。
能の影響を受けた上方舞と、手振りの多い若柳流の踊りをみくらべます。
日時:3月23日(日)15:00開演、14:30開場
出演:山村若(山村流六世宗家)、若柳吉蔵(若柳流五世家元)
司会:小林昌廣(情報科学芸術大学院大学教授)
演目:「座敷舞道成寺」より『山尽くし』 「奴道成寺」より『山尽くし』ほか
↓重ねてアフタートークも開催!!
月イチ☆古典芸能シリーズ
第9回「伝統芸能みくらべ公演アフタートーク」
日時:3月23日(日)17:30~18:30
詳しくはこちらへ http://dev.kac-old.bankto.co.jp/events/11155/
- 日時
-
2014年3月20日 (木) – 2014年3月23日 (日)
Program.A 3月20日(木) 19:00開演
Program.B 3月21日(金・祝)15:00開演
Program.C 3月23日(日)15:00開演
※受付・開場は、開演の30分前からです。 - 会場
- 京都芸術センター 講堂
- 出演
- Program.A 河村晴道、伊藤キム、寺田みさこ ほか
Program.B 露の都、内海英華
Program.C 山村若、若柳吉蔵 - スタッフ
- 舞台監督:大谷みどり(株式会社 京都舞台美術製作所)
照明:宮島靖和(株式会社 リュウ)
音響:大久保歩(有限会社 クワット)
宣伝美術:G_graphics
河村晴道(かわむらはるみち)
能楽師シテ方観世流。昭和35年、京都市生まれ。
父河村晴夫、伯父河村禎二、叔父河村隆司、および13世林喜右衛門に師事。
昭和39年、仕舞「老松」にて初舞台。昭和44年、能「猩々」にて初シテ。今までに「石橋」「猩々乱」「道成寺」「砧」等を披く。
演能のほか、大学での授業、講演を行い、能の普及活動に積極的に関わる。
伊藤キム(いとうきむ)
昭和62年、舞踏家・古川あんずに師事。平成7年、ダンスカンパニー「伊藤キム+輝く未来」を結成。昭和63年、フランス・バニョレ国際振付賞、平成13年、第一回朝日舞台芸術賞寺山修司賞、平成20年、横浜文化賞奨励賞を受賞。平成17年、バックパックを背負って半年間の世界一周の旅に出る。平成23年、「輝く未来」を解散。近年は、若手ダンサーの育成や中高生向けのワークショップ・振付、おやじが踊って給仕する「おやじカフェ」のプロデュースなども行う。京都造形芸術大学客員教授。
寺田みさこ(てらだみさこ)
昭和62年より石井アカデミー・ド・バレエに所属。平成3年より砂連尾理とダンスユニットを結成。平成14年7月「TOYOTA CHOREOGRAPHY AWARD 2002」にて、『次代を担う振付家賞』『オーディエンス賞』受賞。 平成18年以降ソロ活動も開始し、山田せつ子、山下残、白井剛振付作品などに出演。自身の作品としては、平成19年にソロダンス『愛音』や平成25年にグループ作品『アリア』などを発表している。
京都造形芸術大学芸術学部舞台芸術学科准教授。
露の都(つゆのみやこ)
昭和31年、大阪府堺市生まれ。昭和49年、露の五郎兵衛に入門。
日本で第一号の女性落語家となる。男社会といわれる落語界で、女性落語家の草分けとして古典落語一筋に、女性落語家の先頭に立って活躍中。平成17年10月には、女性落語家として史上初の古典落語百選を完遂。平成22年、文化庁芸術祭賞優秀賞受賞。
内海英華(うつみえいか)
昭和53年、旭堂南陵へ女流講釈として入門。昭和54年、新花月にて初舞台。
昭和56年、漫才師内海カッパに師事。昭和57年、故桑原ふみ子(杵屋柳翁)に師事。寄席三味線をはじめる。上方落語界でも数少ない寄席三味線として落語会などで活躍するかたわら、大阪で唯一の「おんな道楽」(三味線漫談)を継承し、活躍している。
平成8年、咲くやこの花賞受賞。平成24年、文化庁芸術祭賞大賞受賞。
山村若(やまむらわか)
山村流六世宗家。平成4年、早逝した母に五世宗家を追贈し、六世宗家山村若を襲名する。初世・二世・友五郎以来、約百年ぶりの男性宗家として女性らしい舞と評され、山村の主流とされている座敷舞(地唄舞)と初世より伝えられる上方歌舞伎舞踊の二つの流れを大切に、伝統の維持継承に力を注ぐ。文楽・宝塚歌劇・歌舞伎の振付・舞踊指導・門下育成に従事する。文化庁芸術祭新人賞・同優秀賞・舞踊批評家協会新人賞・芸術選奨 文部科学大臣新人賞・芸術選奨文部科学大臣賞・日本舞踊協会 花柳壽應賞新人賞・大阪文化祭優秀賞・ベストファーザー賞等受賞。
若柳吉蔵(わかやぎきちぞう)
若柳流五世宗家。二代若柳寿童の三男として京都に生まれる。
昭和62年、流儀の由緒ある名跡、吉蔵を継ぐ。平成10年、五世宗家を襲名する。
寿童の高弟、若柳竜二郎と古金吾に学び、古典や創作舞踊を手がける一方、近年は異流の若手との共演にも挑戦する。京都・宮川町で毎年、「京おどり」の振付、指導も担当している。平成15年、文化庁芸術祭新人賞受賞。平成20年、文化庁芸術祭優秀賞受賞。平成21年、松尾芸能賞 舞踊新人賞受賞。
主催
京都市、京都芸術センター
企画制作:京都芸術センター
助成:平成25年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業
URL
問合せ先
京都芸術センター
Tel.075-213-1000
料金
一般前売券:2,000円
学生前売券:1,500円(当日要学生証呈示)
当日券:2,500円(一般、学生とも)
3公演通し券:5,000円
※全席自由席
チケット/申し込み
●京都芸術センター
TEL.075-213-1000
●京都芸術センター窓口
(10:00~20:00)
●京都芸術センターウェブサイト
下記予約フォームより、お申込みください。チケットは、当日受付にてご精算いただいた後にお引き取りいただきます。
http://481engine.com/rsrv/webform.php?sh=2&d=f60565d196
*システム協力:シバイエンジン
●チケットぴあ TEL:0570-02-9999
(Pコード 433‐884)